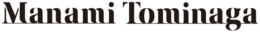20代の頃、10ヶ月だけ海外旅行のツアーコンダクターをしていた。
ある新聞に掲載されていた「海外旅行ツアーコンダクター求む!」という募集を見て、「いろんな国に行けるかな」という程度の動機で応募した。確かにいろんな国に行けたのだが、ツアコンの仕事は想像を絶する困難な仕事であった。
その年の秋、北米コースのツアーを任された。そのツアーにはいろいろな属性の人々が参加していた。当時は若干珍しかったのではと思うが、今ではまったく珍しくない、今でいうところのお一人様も参加していた。女性だった。ここでは宮明さんという仮名を使うことにする。
一人だと、だから仕方ないと言ってはいけないのだが、どうしても食事時に残った一席に座ることを余儀なくされることが少なからずあった。私も他のグループの人々もご一緒にどうですかと誘ってはいたのだが。でもね、一人で食べるほうが気兼ねなくていいかなあ、と思うこともあった。まだ20代だった私は、おそらく自分よりも数十年年上の大人が何を望むのか考えあぐねていた。
いろいろあったが、旅も終盤に近付いてきた。その日宿泊したホテルのディナーはビュッフェだったと記憶している。ホテルにはその他大勢のお客さんもおり、ツアーグループに割り合てられたテーブルは武骨なブロック区画で、うまくいろんな人数のグループが座るのに工夫が要り、宮明さんに少し待ってもらわねばならなかった。そして私はそのとき、何かの急な事情で一緒に夕食を食べられなかった。
その夜、ホテルの部屋でやっと仕事が終わってぼんやりしていたとき、部屋の電話が鳴った。出てみると宮明さんだった。
夜中にごめんなさい、失礼なのはわかっているのだけれど、と、前置きしてから宮明さんはぽつりぽつりと話し始めた。
私ね、一人で旅をするのは初めてなの。一人とはいえこれはツアーだけど。これまでは夫と二人で一緒に旅してきたの。まるっきり一人で旅することができそうにも無いと思って、ツアーに参加してみたんです。え?席のこと?いいえ、席のことはいいんです。それはなんとなくそうなるとわかっていたの。そんなの冨永さんのせいじゃないんです。周りのみなさんにも気を使っていただいて、逆に申し訳ないくらいです。
それでも今日のディナーでは、誰がどこに座ればみんなにとって公平なのか。そのために宮明さんに座るのを待ってもらわねばならなかった。それは本当に申し訳なかった。
冨永さん、そんなこといいんです。そうじゃないの。私ね、夫と2人だと、どんな席だろうが、そもそも席がなかろうが構わなかった。日本でも海外でも、2人でなんとかやってきたんです。席が無かったらお願いして作ってもらったくらいよ。ずうずうしいね、と笑ったりするのも楽しみのひとつだったの。でも自分一人だけだと足がすくんでそれができなかった。どう動いていいかもわからなかった。できると思ったんだけど甘かったんだと思う。私の夫はね、昨年亡くなってしまったんです。
私は受話器をもってまま何も言えず黙っていた。受話器を通してしばらく沈黙が続いた。
夫は国内外の出張でとても忙しい人だった。夫はね、橋梁、つまり橋専門のエンジニアだったの。橋が大好きで、世界中、特にヨーロッパの橋を訪れて研究していたの。ヨーロッパの橋に関する本を出版することになったので、取材でさらに多くの橋を訪れていた。私も取材に同行したんです。でも夫はその本を出版してすぐに亡くなってしまったの。
どんなに忙しくとも、毎年誕生日も一緒に祝ったの。それが夫婦でいることの一つの証だったから。そしてね、今日は私の誕生日だったんです。とても一人で誕生日を過ごせそうにないと思ったのだけど、海外だったら、団体ツアーだったら、大勢に囲まれているからなんとか一人でも過ごせるだろうと思ったんです。
宮明さんの静かな嗚咽を聞きながら、私は途方もない虚脱感に襲われた。
ツアー参加者の誕生日を祝うのは大事なイベントだ。このとき、グループには様々な希望や属性を持つ参加者がおり、方々に気を使う中、宮明さんの誕生日の目印を見逃していたらしかった。それまで、何はともあれ、何は無くとも、どれほど鈍くさいことをやらかしても、参加者の誕生日を祝うことだけは忘れていなかったというのに。
配偶者が亡くなった後、一人で外食することも映画鑑賞することもできなくなった人がいる。亡くなった配偶者の衣類をどう片付ければよいの分からず、長いことそのままにしておく人もいる。新聞の折込広告に書かれた「夫婦割り」という文字を見て新聞を丸めて捨てる人もいる。自分が一人でいることを認識せざるを得ない物事は日常生活にあふれているが、それでも残された片方は日々を生きていくしかない。
どうすれば少しでも宮明さんへの謝罪になるのか。ちょっとしたプレゼントをと思っても、夜遅いのでホテルの売店は締まっている。しばし考え、このツアーではワイナリーにも訪問したので、そのさいに入手したワインがあったと思いついた。それを持って宮明さんの部屋を訪れ、お誕生日のプレゼントとして手渡した。
翌朝、宮明さんとロビーで出会った。どことなくすっきりした表情の宮明さんは、私を見つけるとニコニコと歩み寄ってきてこう言った。
「冨永さん、昨夜は本当にごめんなさいね。団体ツアーのツアコンさんなのに、私個人のことで冨永さんに頼りすぎてご迷惑おかけしたと思います。そしてワインを本当にありがとう。きっと冨永さんが自分のために買ったものよね。でもありがたくいただいて、日本でじっくり味わうのを楽しみにしています。そのお返しといってはなんですけど、夫の本をぜひ読んでいただきたいので、お送りしてもいいでしょうか」
後日、その言葉通り、ヨーロッパの橋をテーマとした本が送られてきた。丁寧な手書きの手紙も添えられていた。
あれからほぼ四半世紀が経った。その間、本を開くことはほとんど無かったが、その本はどれほど引っ越ししても、どれほど断捨離しても、どれほど複雑かつ煩雑な梱包と荷ほどきを繰り返しても、必ず私の本棚に収まることになった。自分の人生の要で役立つ良書のひとつとなることが分かっていたからだと思う。
この6月、中欧4カ国を巡るドナウ川リバークルーズの取材が決まった時、この本を書棚から引っ張り出した。そして、収録されている30の橋のうち、2つに印を付けた。
その一つはレーゲンスブルグの橋だ。
乗船に先んじてレーゲンスブルグに入った。チェックインして、その足でドイツ最古の石橋とされるレーゲンスブルグの橋へ歩いた。それから、レーゲンスブルグ大聖堂へと向かった。
本の「レーゲンスブルグの橋」の章に、こんな一節が書かれている。「レーゲンスブルグ大聖堂の前にあるホテルに妻と宿泊した。橋のことを抜きにしてもまた訪れたい街だ」
おそらくそのホテルと思われる建物の1階はカフェレストランになっており、大聖堂の正面全景を臨める屋外のカフェスペースのテーブルは、その週に街のフェスティバルが開かれることもあってか大いに人で賑わっていた。
ヨーロッパの照り付ける太陽、石畳に反射する太陽の熱い光。それらも日陰に入るとすべて効力を失い、乾いた心地よい空気だけが肌を覆う。私はご夫婦が座ったかもしれないテーブルを選び、腰かけた。
せっかくドイツにいるのだし、リースリング、ソーセージ、そしてポテトを頼んだ。そして本の「レーゲンスブルグの橋」の章を開いて読み返した。本には宮明さんの手紙を挟んだままにしてある。なんとなく、この本と手紙を離れ離れにしてはいけないように思ったのだ。
著書の前書きには「この本を妻へ贈る」と書かれている。その文を指でなぞりながら、乾いたのどを潤すためにリースリングを飲んだ。