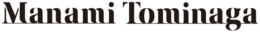20代の頃に約5年間、英語を教えていた。
大学卒業後に就職したのは全国津々浦々に展開する大手英会話スクールだった。(Aで始まるあれ)そこで下は0歳児から上は70歳までの生徒に英語を教えた。
ある小学校高学年のクラスに、とても可愛らしく成績優秀な少女がいた。子役タレントの杉咲花ちゃんによく似ていたので、ここでは花ちゃんと呼ぶことにする。
花ちゃんはなぜかわたしによくなついてくれた。授業の前後によくおしゃべりをしたし、その内容は先生と生徒というよりは友達同士のような気軽さがあった。新米の英語教師だった私の授業は、熱意はあれど深みには欠けていたと思う。多分、その熱意の部分が子供の共感を呼んだのか、花ちゃんは「先生の授業、たのしい!」と言ってくれた。社会に出たばかりの私は、ほめられるよりは怒られるほうががぜん多かったので花ちゃんの言葉は大きな救いだった。
しかし私の絶大な味方であり心の拠り所でもあった花ちゃんが、親御さんの転勤で九州の大都市に引っ越すことになってしまった。最後の日はクラスのみんなが泣いた。私も泣いた。花ちゃんがいなくなったクラスは変わらず子供の熱気にあふれているのだが、大事なピースが失われた未完成のパズルのようになったと感じた。
数ヶ月後のある日、自宅に花ちゃんから電話があった。友達と遊ぶから一人で広島に帰ってくるという。
「先生のところに泊まっていい?」という。
当時私は実家で母と暮らしていた。別に実家を見られても困らないし、久しぶりに「味方」に会えるような気がして「いいよ!」と受け入れた。
初秋の晴れた土曜日に花ちゃんはやってきた。数か月前よりも少し大人びた気がする。母が作ってくれた夕食を差し向かいで食べながらお話をした。「新しい学校どう?」とか、「友達できた?」とか、そんなたわいもない話をしながら数ヶ月のギャップを縮めていく。そんななか、なんとなくお互いの「未来」に関する話題へと移っていった。花ちゃんは「多分、会社で働くと思うよ」という。
「先生はずっと英語の先生をするの?」
「そういうふうに思ってないけど、まだどうなるか分からない」
「じゃあ何になるの?」
「いろいろやりたいことはあるよ。でも今の仕事もすごく大変で、きちんと考える余裕がないんだよ」
「ふうん。いつ余裕ができるの?」
まったくもって良い質問だった。ほんと、そんな余裕、いつできるんだろう。時間もコネもお金もたいしてなし、ついでに彼氏もいなかった。なんか、ほんとにないないづくし。誰も助けてくれそうにないし、いつどうするかは自分で決めなければならない。黙っている私を見て花ちゃんはこう言ってくれた。
「きっとできるよ。私もがんばるね」
私は成人していたとはいえ、常に「数字」で結果を求められる社会の厳しさを肌身で感じている、ちょっと大きめの子供のようなものであった。未来に大きな希望を抱くとともにその不確かさに圧倒されていることにおいて、私と花ちゃんはほぼ同等の立場にあったと思う。とはいっても、励まさなければならないのはどっちかというと年上の私。なのに逆に励まされてしまった。
翌日、花ちゃんは九州に帰っていった。実家の玄関先で、何度も振り返りながら歩き去っていく花ちゃんを見送った。それが花ちゃんを見た最後になった。
花ちゃんが帰った後、母はこう言った。
「友達の家でもなく、親戚の家でもなく、うちに泊まるとはね。あんたがよほど好きなんだよ」
私の母は筋金入りの教育者である。毎日、私を見てハラハラして見ていたことだろう。授業だけでなく、生徒やその保護者への対応に加え、営業成績達成の責任をもたされていたことで疲れきっていたから。
ともあれ、花ちゃんの「きっとできるよ。私もがんばるね」との励ましの言葉を時々思い出しながら、その後の人生を歩んできたのだ。
今回の里帰りで、久々に路面電車に乗った。ふと、少し離れた席に座ったとても魅力的な女性に目が留まった。その女性を見ていると、私の記憶にある花ちゃんの姿がよみがえってきた。
もしかして、花ちゃん?
そう思い、失礼にならないように何度か盗み見た。花ちゃんは今は40歳くらいになっている。その女性はそんな年の頃合いに見える。声をかけてみようかなと思ったが、いくら似ているとはいえ自分の記憶を信じるには時が経ちすぎている。
あれこれ思い巡らすうち、その女性は電車を降りていった。
その女性が花ちゃんだったのかどうか。会いたいから、幻みたいなものが見えたかな。でも、私はとても幸せな気分になった。
40歳の花ちゃんに会って、いろいろと話して成果を報告してみたい。
花ちゃんに「きっとできるよ」と言われたから、なんとか「がんばってきた」といつか言えたらいいなと思う。
追伸:
広島の中尾醸造の酒、「幻」はほんとに美味しい。おすすめ。